個人事業主に「給与」はある?経費の基本とともに解説! | レバテックフリーランス
個人事業主に「給与」はある?経費の基本とともに解説!
個人事業主として新しくビジネスを始めたばかりのタイミングでは、なにかとわからないことが多いものですよね。「給与の考え方がわからない」「経費計上について詳しく知りたい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
この記事では個人事業主の方向けに「給与」の考え方の基本をお伝えします。税務関連で押さえるべき知識も紹介しているので、ぜひ最後までお読みください。
個人事業主に「給与」はあるの?
個人事業主に「給与」という概念はありません。個人事業主にとって、事業で得た利益は給与ではなく収入として扱われます。この点は、会社員の給与システムとの根本的な違いです。事業収入から必要経費を差し引いた「所得」が、個人事業主の実質的な収入となるのです。
なお、従業員を雇用する場合は、彼らに対して「給与」を支払うこととなります。
【個人事業主必見】従業員への給与は経費計上できる
個人事業主が従業員を雇用して支払う給与は、全額を経費として計上できます。これは事業を継続するために必要な支出として認められているからです。従業員の給与は「給料賃金」という勘定科目で経費計上します。
従業員への給与を経費計上することで、所得を減らし、結果的に所得税や住民税の負担を軽減できる場合も少なくありません。
なお、給与を支払う際には源泉所得税の徴収義務があり、さらに社会保険の加入義務が発生する場合がある点には留意してください。
従業員へ支払う給与の計算方法
従業員への給与計算には基本的な流れがあります。まず総支給額を決め、そこから社会保険料や所得税などを差し引いて手取り額を算出します。
詳しくは下記のステップを参考にしてみてください。
- 1.総支給額の決定:基本給+各種手当(残業手当、通勤手当など)
2.社会保険料の控除:健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料
3.所得税の計算・控除:「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて計算
4.住民税の控除:従業員の前年の所得に基づいた金額
5.手取り額の計算:総支給額−(社会保険料+所得税+住民税)
給与計算は複雑なため給与計算ソフトの活用や、必要に応じて税理士に相談するのも一つの選択肢です。
従業員へ給与を支払う際の3つのポイント
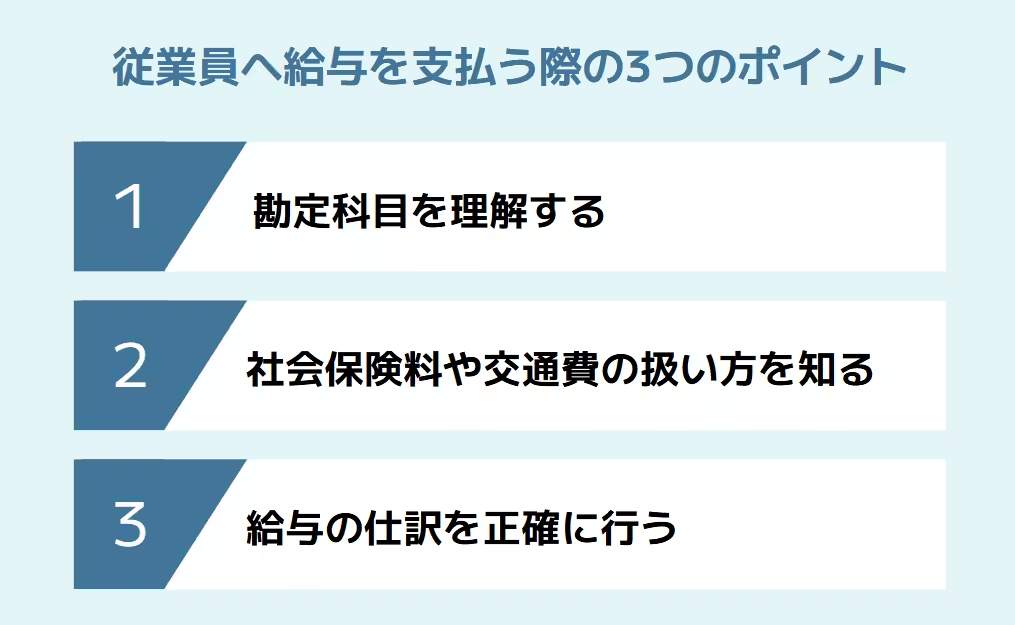
続いて従業員への給与支払いに際して押さえておくべき3つのポイントをお伝えします。
勘定科目を理解する
従業員への給与支払いにおいて、正しい勘定科目を理解しておくことは大切です。給与は前述した通り、「給料賃金」という勘定科目で処理されます。これにより、事業の会計が明確になり、確定申告もスムーズに進められるようになるのです。
なお、給料賃金以外にも、役員報酬(法人の場合)や雑給(アルバイトやパートへの支払い)など、支払う相手や雇用形態によって使い分ける勘定科目があります。開業したばかりの方にとっては覚えることが少々多いかもしれません。しかし、適切な勘定科目で処理することは税務の観点からも重要であるため、適切に行うよう心がけましょう。
処理の正確性を期すうえでは、会計ソフトの導入も一案です。初期投資は必要なものの、長期的には業務効率化につながります。
社会保険料や交通費の扱い方を学ぶ
従業員の給与には、本給以外に、社会保険料や交通費などの項目があります。これらの扱い方も正しく理解しておきましょう。
まず、社会保険料は従業員と事業主で折半するのが基本です。また、交通費については、1か月あたり15万円以下であれば非課税となります。ただし、通勤のルートが合理的かつ効率的と認められない場合はこの限りではありません。同様にグリーン車を利用する場合も課税対象となるため、注意しましょう。
従業員給与の具体的な仕訳例を確認する
従業員給与の仕訳を正確に行うことで、経理処理がスムーズになります。給与支払い時の基本的な仕訳例を見てみましょう。下記は、総支給額30万円、社会保険料(従業員負担)4万円、所得税2万円のケースです。| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給料賃金 | 300,000円 | 預金 | 240,000円 |
| 預り金(社会保険料) | 40,000円 | ||
| 預り金(所得税) | 20,000円 |
この仕訳では、「給料賃金」が経費として計上され、実際に支払う手取り額は「預金」、控除した社会保険料と所得税は「預り金」として処理します。また、事業主負担の社会保険料がある場合は、別途「法定福利費」として経費計上します。
従業員を雇用する際の流れ
従業員を雇用する際には、いくつかの手続きが必要です。ここでは従業員雇用の流れを5つのステップに分けてお伝えします。
労働保険の加入手続きを進める
従業員の雇用に際して、まずは労働保険(労災保険と雇用保険)への加入が必要です。加入は義務であり、違反すれば罰則の対象となる場合があります。
なお加入手続きは、従業員を雇用してから10日以内に行う必要があり、手続きは管轄の労働基準監督署で行います。この際の必要書類は「保険関係成立届」「概算保険料申告書」の2点です。ただし、雇用保険の適用事業である場合は上記にくわえ「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」も必要になります。
なお、労災保険はすべての従業員が対象ですが、雇用保険は31日以上雇用される見込みがあり、週20時間以上働く従業員が対象となります。
手続きは煩雑になりがちなため、社会保険労務士に相談するのも一つの方法でしょう。
法定四帳簿を作成し保管する
従業員を雇用する際には、法定四帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、年次有給休暇管理簿)の作成と保管が法律で義務付けられています。これらは労働基準法に基づく重要な書類です。
労働者名簿には従業員の氏名、生年月日、住所などの情報を記載します。賃金台帳には毎月の給与計算の詳細を、出勤簿には勤務時間や休暇を記録します。また2019年より労働者の有給休暇の取得状況を記録する年次有給休暇管理簿の作成・保管も必須となりました。
これらの帳簿は税務調査や労働基準監督署の調査の際に確認されることがあるため、正確名作成と適切な保管を心がけてください。なお、クラウド型の労務管理システムを利用することで、効率的に情報を管理できるようになります。
労働条件通知書を交付する
さらに、労働条件通知書を交付する必要もあります。労働条件通知書には、雇用条件を明確化して従業員とのトラブルを防ぐ役割があります。
記入項目としては、給与、勤務時間、休日、社会保険の加入状況など、雇用に関する重要事項が挙げられます。これらを漏れなく記載したうえで、雇入れの際に書面で交付しなければなりません。
なお、在宅勤務の可否やフレックスタイム制の採用など、特殊な勤務条件がある場合は、それらも明記しておきましょう。
参考:労働条件通知書|厚生労働省
税務署等への届け出を行う
最後に、税務署などへの届け出も滞りなく行いましょう。主な届け出には「給与支払事務所等の開設届出書」があります。これは従業員を雇い入れてから1ヶ月以内に税務署へ提出すしなければなりません。
また、社会保険に加入する場合は、年金事務所への必要書類の提出も忘れないようにしましょう。必要書類の詳細については下記を参考にしてください。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者異動届(該当する方がいる場合)
従業員が常時5人未満の場合は任意ですが、5人以上になると加入が必須となることを覚えておきましょう。
一連の手続きに際して不明点がある場合は、税理士や社会保険労務士へ相談するのが賢明と言えます。
参考:事業主の方へ ~従業員を雇う場合のルールと支援策~|厚生労働省
家族への給与は経費にできる?
個人事業主が家族を従業員として雇い、給与を支払うことは可能ですが、経費として処理することは原則としてできません。
ただし、家族が生計を別にしており、かつ他の従業員と同様の待遇(業務内容および評価基準)のもとで給与を支払っている場合は、経費計上が可能になります。
家族と生計をともにしている場合、後述の青色申告の特別控除制度を上手く活用することで、節税を図ることも可能です。
個人事業主が押さえておきたい税務関連の知識
続いて、個人事業主として必要な税務知識を2点お伝えします。
確定申告について
個人事業主となったら、毎年確定申告を行う義務も発生します。確定申告とは、1年間の所得と税額を計算し、納税する手続きです。後述のとおり、「青色申告」と「白色申告」の2パターンがあり、下記にそれぞれの必要書類を記します。
必要書類【青色申告】
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 確定申告書に添付する控除に関する書類(控除が必要な場合のみ)
- 取引先からの支払調書(源泉徴収となる取引がある場合のみ)
- 源泉徴収票
必要書類【白色申告】
- 確定申告書
- 収支内訳書
- 確定申告書に添付する控除に関する書類(控除が必要な場合のみ)
- 源泉徴収票(給与所得などがある場合のみ)
- マイナンバーに関する書類
なお、確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までで、この期間に前年分の確定申告を行います。e-Taxを利用すればオンラインでも手続きが可能です。
青色・白色申告の違い
個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。それぞれに特徴と違いがあるため、自分に合った申告方法を選びましょう。
青色申告は、事前に「青色申告承認申請書」を提出し、複式簿記で帳簿をつける必要がありますが、最大65万円の特別控除が受けられます。また、赤字を3年間繰り越せるというメリットもあります。
一方、白色申告は手続きが比較的簡単ですが、青色申告と比べると税務上のメリットは少なくなります。両者の違いについては以下の表をご覧ください。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円 | なし |
| 帳簿方式 | 複式簿記(原則) | 簡易な記帳 |
| 赤字の繰越 | 3年間可能 | 不可 |
| 手続きの手間 | やや複雑 | 比較的簡単 |
それぞれ一長一短があるため、事業の状況を鑑みつつ、より適したほうを選んでみてください。
以下の記事では、個人事業主の確定申告について詳しく解説しています。併せてお読みください。
フリーランスの確定申告まとめ!青色申告と白色申告の違いも解説
経費計上できる・できないもの
確定申告では、経費の計上も重要なポイントとなります。開業したばかりの方は、どの支出が経費計上可能なのか把握しておく必要があります。下記を参考にしてみてください。
▼経費計上できるものの例
- パソコン、ソフトウェア、開発ツールなどの購入費
- インターネット接続料、サーバー利用料
- 事務所家賃(自宅の一部を事務所にしている場合は按分)
- 取引先への交通費、出張費
- 書籍や参考資料の購入費
- セミナーや勉強会の参加費
▼経費計上できないものの例
- 完全に私的な用途の交際費
- 自宅の生活費に関わる部分
- 罰金や過料
経費の線引きが難しい場合は、事業との関連性を明確に説明できるかどうかが判断基準になります。不明な点があれば、税理士に相談することをおすすめします。
経費計上について
個人事業主にとって、適切な経費計上は利益の最適化に直結します。
経費計上のポイントは、事業との関連性が説明できることです。たとえば、エンジニアのフリーランスの方の場合、開発用のパソコンやソフトウェア、技術書籍などは明らかに事業に必要なものですので、全額経費として計上できます。
一方、自宅兼事務所の場合、家賃や光熱費は事業使用部分を按分して経費計上します。
| 経費項目 | 計上方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 開発機器 | 10万円未満は消耗品費、 10万円以上は減価償却 |
私用との按分が 必要な場合あり |
| ソフト ウェア |
10万円未満は消耗品費、 10万円以上は減価償却 |
サブスクリプションは 支払時に経費計上 |
| 通信費 | 事業割合を按分して計上 | 私用との線引きが重要 |
| スキル アップ費用 |
研修費・新聞 図書費として計上 |
現在の事業に関連 するものが対象 |
| 交際費 | 取引先との会食など事業関連のもの | 領収書に相手先や目的を記録 |
経費計上の適切な管理は、節税につながるだけでなく、事業の収支状況を正確に把握するためにも重要です。日々の記録をしっかりと行いましょう。
個人事業主が経費を扱ううえでの注意点
個人事業主が経費を扱う際には、いくつかの注意点があります。正しい経費処理を心がけることで、税務調査などのリスクを減らし、節税効果を得ることができます。
まず、プライベートと事業の支出をしっかり区別することが重要です。混同すると税務調査の際に問題となる可能性があります。事業用の銀行口座と個人用の口座を分けて管理するのがおすすめです。
そのうえで、すべての取引の証拠となる領収書やレシートを保管しておきましょう。電子データでの保存も認められていますが、一定の要件を満たす必要があります。書類の保存期間は原則として7年間です。特に重要な契約書などは長期保存を心がけましょう。デジタル化して保管すれば場所も取らず、検索も容易になります
また、経費の過大計上は避けるべきです。たとえば、完全に私用のレストランでの食事を接待交際費として計上すると、税務調査で指摘されかねません。
※本記事は2025年6月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
簡単4ステップ!スキルや経験年数をポチポチ選ぶだけで、あなたのフリーランスとしての単価相場を算出します!
※相場算出に個人情報の取得はおこないません。
役に立った/参考になったと思ったら、シェアをお願いします。





