【2025年版】フリーランスの保険ガイド|定番のおすすめサービスや健康保険組合 | レバテックフリーランス
【2025年版】フリーランスの保険ガイド|定番のおすすめサービスや健康保険組合
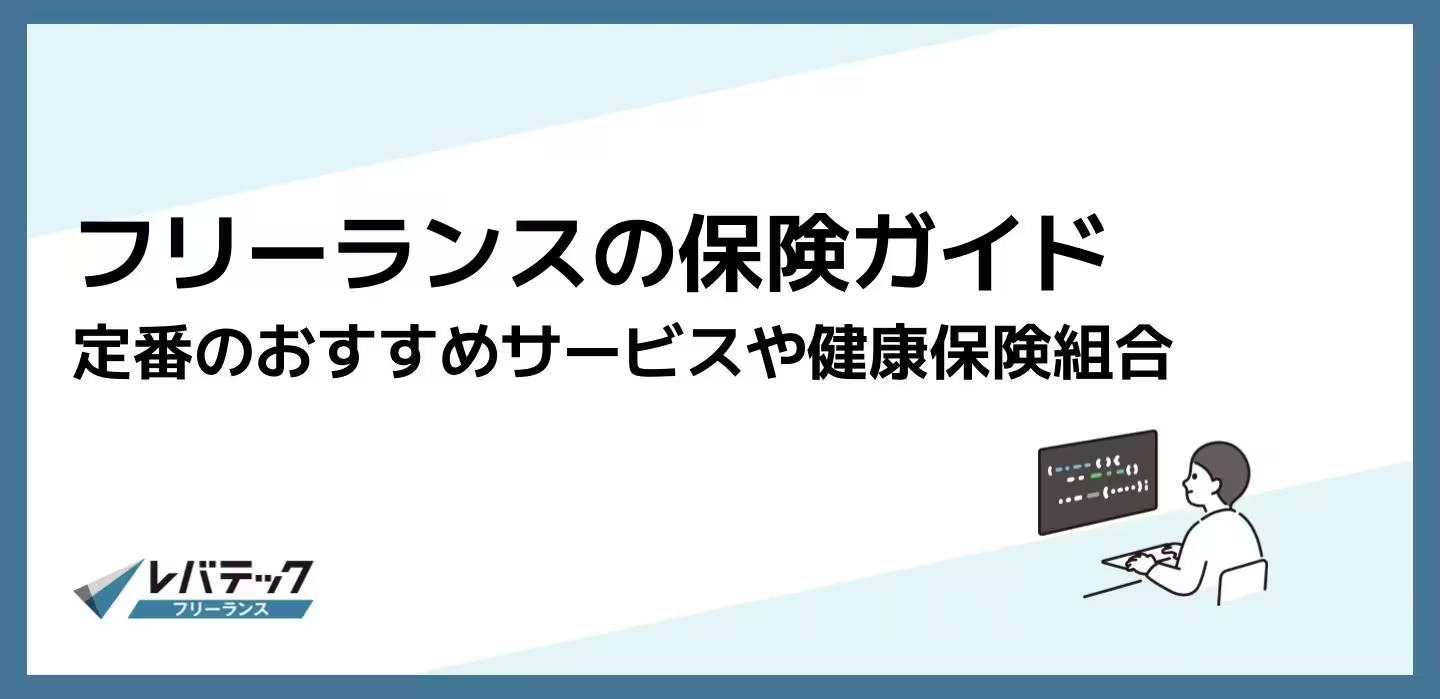
フリーランスとしてどのように保険を選べばよいのか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。本記事では、加入できる健康保険組合や民間サービス、それぞれのメリットとデメリット、保険料を抑える方法などを解説していきます。
目次
フリーランスが知っておきたい保険の基礎知識
日本は国民皆保険制度を導入しているため、フリーランスも公的な医療保険に加入しなくてはいけません。フリーランスと会社員の保険の違いなど、必ず知っておきたい保険の知識を解説します。
フリーランスと会社員で加入する保険は違う
会社員が加入する健康保険は「一般被用者保険」、フリーランスが加入するのは「国民健康保険」です。
会社員が加入する「一般被用者保険」の保険料は、会社が半額負担し、残り半分は給与から天引きされます。家族は扶養として加入できるほか、出産手当金や傷病手当金などもあり、国民健康保険よりもさまざまな保障があります。
一方、フリーランスが加入する「国民健康保険」にはこうした手当はなく、全額自己負担です。扶養も存在しないため、家族もそれぞれ国民健康保険に本人として加入し、保険料を支払う必要があります。
国民健康保険料は収入や自治体によって異なる
国民健康保険料は、各自治体によって算出方法が異なり、収入や世帯人数、年齢などによっても異なります。
たとえば年収が200万円の場合約14万、300万円で約20万ほどの保険料です。1年間の金額のため、毎月の金額は12ヶ月で計算できます。
自分の場合はどれくらいの保険料がかかるだろう、と気になる場合は役所のホームページなどで確認しましょう。
民間の保険サービスに入る選択肢もある
フリーランスは会社員や公務員と比べて、公的医療保険や年金などが手薄です。保障内容に生じる格差を埋めるため、民間の保険サービスへの加入も検討してみてください。具体的な民間の保険サービスなどは後ほど紹介します。
フリーランスが加入できる保険の選択肢5つ
フリーランスが加入できる保険の選択肢として、国民健康保険への加入や勤めていた会社の健康保険任意継続があげられます。また、家族の健康保険の扶養に入ったり、業種特化の健康保険組合に加入したりもできます。
それぞれ詳しく解説していきますので、保険の加入先を決める参考にしてください。
国民健康保険に加入する
国民健康保険は、日本国内に住所を有する個人事業主などが加入する健康保険です。国民健康保険に加入する場合は、住んでいる市区町村の役所で加入手続きを行いましょう。
保険料は、医療分保険料と支援金分保険料、そして40歳以上60歳未満の人は介護分保険料の3つで構成されています。これらを合算した金額を支払います。
国民健康保険に加入するメリットは、所得額が基準値よりも低くなった際、自動的に減額してもらえることです。デメリットは、所得額に応じて保険料が高くなるほか、扶養家族分の保険料も上がることなどです。
保険料の税率は市区町村によって異なり、前年度の所得をもとに決定します。詳細は住んでいる市区町村のWebサイトを確認してください。
勤めていた会社の健康保険任意継続をする
健康保険任意継続は、就業先で加入していた健康保険に一定期間延長して加入できる制度です。退職後2年間に限り、勤めていた会社の健康保険に加入できます。
対象となる条件は、退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることです。また、任意継続したい人は、退職後20日以内に申請しなくてはなりません。
健康保険任意継続制度のメリットは高所得の場合、国民健康保険よりも保険料が少なくなる可能性があることです。また、保養所や健康診断の受診補助などを引き続き利用できることもあるでしょう。
デメリットは、自己都合で切り替えができないことです。「家族の扶養に入りたい」と思っても、切り替えられません。任意継続する際はよく考えてするようにしましょう。
さらに、健康保険任意継続は最長で2年までしか継続できません。滞納に厳しく、支払いが1日でも遅れたら脱退させられてしまう場合もあります。また、保険料は全額本人負担のため、会社員時代よりも負担が大きくなります。
家族の健康保険の扶養に入る
フリーランスも、家族の扶養に入れます。扶養に入るには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 年間収入が130万円未満である
- 扶養者との続柄が3親等内である
家族の健康保険の扶養に入ると、被扶養者の保険料は無料となるほか103万円までの収入であれば所得税もかかりません。配偶者控除により、扶養者の所得税や住民税額が減るというメリットもあります。
デメリットは、加入条件に収入の制限があるため、フリーランスとしての活動を抑えなければならないことです。支払っている保険料がない分、将来的にもらえる年金も少なくなることも踏まえて検討するようにしましょう。
業種特化の健康保険組合に加入する
建設や理美容、食品など、特定の業種を加入対象とする健康保険組合に加入するのも1つの方法です。
フリーランスが加入する健康保険として名が知られている2つの健康保険組合について紹介します。加入要件や保険料は各団体によって異なるため、自分が該当する健康保険組合を確認したうえで検討しましょう。
文芸美術国民健康保険組合
文芸美術国民健康保険組合は、文芸や美術といった著作に関わる仕事をしている人を対象とした保険です。Webデザイナーやイラストレーターなどとして働くフリーランスなら、加入できる可能性があります。
保険料は組合員の収入にかかわらず一定で月額24,800円、家族は14,800円です。満40歳から64歳までの被保険者は、介護保険料として月額5,700円追加でかかります。
デメリットは同組合の加盟団体の会員になり、保険料とは別に団体の会費も支払う点が挙げられます。ただし、保険料は加入区分で決まるため、収入による保険料の変化がありません。
したがって、収入が増えても保険料が上がらない点がメリットだといえるでしょう。
東京美容国民健康保険組合
東京美容国民健康保険組合は、美容の業務に従事している人を対象とした健康保険組合です。美容師だけでなく、事務や会計も加入できます。ただし、事業所が東京にある場合に限るため、地方に事業所がある方は加入できません。
保険料は組合員の収入にかかわらず一定で月額19,000円、家族は8,500円、義務教育就学前の未就学児は5,000円です。満40歳から64歳までの被保険者は、介護保険料として1人あたり月額3,000円が追加でかかります。
メリットとしては、文芸美術国民健康保険組合同様、保険料は加入区分で決まるため、収入による保険料の変化がない点です。
独立した際の保険の切り替え手続きの流れ
フリーランスとして独立したら「被用者保険」から「国民健康保険」への切り替えが必要です。
国民健康保険に加入する場合や任意継続する場合など、ケースごとに解説をしていきます。切り替え手続きには期限が短いものもあるため、早い段階で確認しておきましょう。
なお、切り替えにともない会社で加入している保険を解約する必要がありますが、解約手続きは会社がします。解約において何か書類や特別な手続きをする必要はありません。
国民健康保険の手続き方法
会社を退職後、フリーランスが国民健康保険に切り替える場合、住んでいる自治体の役所で手続きします。なお、手続きは会社を退職してから2週間以内であるため、必要なものは早めに準備しておきましょう。
手続きに必要なものは以下のとおりです。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(マイナンバーが確認できるもの)
- 健康保険資格喪失証明書(離職票、退職証明書でも可)
- 印鑑
自治体の役所での手続き完了後は、保険料の通知書が郵送されます。通知書で保険料の支払い開始月を確認し、保険料を納付しましょう。
なお、会社員時代に社会保険の扶養となる家族がいた場合、注意が必要です。国民健康保険では、家族の保険料も納めなくてはいけません。
勤めていた会社の健康保険を任意継続する方法
勤めていた会社の健康保険をフリーランスになっても任意継続する場合、住所地を管轄する全国健康保険協会の支部で手続きを行います。退職後20日以内に行う必要があります。
手続きには、「任意継続被保険者資格取得証明書」が必要です。全国保険健康協会のホームページからダウンロード可能です。退職日が確認できる書類の提出は任意ですが、提出するとより早く保険証を発行してもらえます。
家族の健康保険の扶養に入る方法
全国健康保険協会を例に、フリーランスが家族の健康保険の扶養に入る手続きを紹介します。全国健康保険協会で扶養に入る場合、事業主経由で国民年金第3号被保険者関係届か、被扶養者(異動)届を提出します。
手続きの際、必要になる書類は以下のとおりです。
- 被保険者の住民票
- 被保険者の戸籍謄本(戸籍抄本)
条件によっては上記以外にも書類が必要になるため、事前に確認しておきましょう。
国民健康保険組合に加入する方法
国民健康保険組合は、組合によって手続きが異なります。たとえば文芸美術国民健康保険組合の場合、文芸・美術・著作活動を行っており、組合の加盟団体の一員であることが加入条件です。また、手続きに以下の書類が必要です。
- 加入申込書
- 加入団体証明書
- 所得税の確定申告書B控え
- 預金口座振替依頼書
- 住民票
- 作品例
文芸美術国民健康保険組合は、新規加入の申込締切日を毎月5日に設定しており、審査が通れば翌月1日から加入できます。不備があると加入が遅れるため、書類は提出前にしっかり確認しておきましょう。
フリーランスが健康保険料を安く抑える方法
「毎月払う健康保険料の負担を少しでも減らしたい…」と思ってしまいがちなフリーランスの保険事情。保険料が安い自治体へ転居や国保・フリーランス向けの組合に加入するなどの方法で抑えられます。
ほかにも、軽減・減免制度を利用したり家族の扶養内でおさまるように活動するといったコツもあります。ここでは、こうしたフリーランスが支払う健康保険料を抑える方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
保険料が安い自治体へ転居する
国民健康保険料率は、市区町村によって異なります。したがって、保険料率を調べたうえで保険料が安い自治体へ転居すれば、支払う保険料を抑えられます。
所得が基準を下回る場合は軽減・減免制度を利用する
国民健康保険には、所得基準を下回る世帯に対し、7割・5割・2割のいずれかの減額割合を適用する制度があります。
また、特別な事業により保険料の納付が困難な方に対し、減免・納付猶予制度も設置されています。保険料の支払いが難しい方は、対象となるかを確認してみましょう。
経費を適切に計上して節税する
経費を増やし課税所得を減らせれば、支払う国民健康保険料の負担の軽減に繋がります。なお、事業と関係のない費用は経費として計上できないため注意しましょう。
また、フリーランスは国民健康保険料を経費にできません。
国民健康保険組合やフリーランス向けの組合・協会に加入する
収入が多いフリーランスは収入で保険料が変動する国民健康保険よりも国民健康保険組合のほうが料金が安くなる可能性があります。
さまざまな国民健康保険組合やフリーランス向けの組合・協会が存在しますが、業種などによって加入できるものは異なります。自分の職業で入れる組合の料金と現在の保険料を比較して安い方を選択すると良いでしょう。
家族の扶養内でおさまるように活動する
家族の健康保険に入れば保険料や税金が抑えられます。ただし、扶養内の活動では、長期的に見て成長や案件獲得のチャンスを逃す要因にもなりかねません。扶養内で活動するかは、将来的なビジョンも視野に入れたうえで検討しましょう。
フリーランスの場合リスクに備える保険の加入もおすすめ
フリーランスは会社員や公務員と比べて、医療保険や年金が手薄な傾向があります。そこで、オプションで民間保険に加入してその差を補うのがおすすめです。
まずは各種リスクにどのくらいさらされているかを把握し、紹介していく保険の中から必要なものをピックアップしていきましょう。
フリーランスに想定される経済的リスク
フリーランスは、怪我や病気で働けなくなったときや老後に経済的リスクが想定されます。それぞれの状況における公的保険制度の保障範囲と想定される経済リスクを解説します。
怪我や病気で働けなくなったときに想定される経済的リスク
会社員の場合、働けなくなったときには「傷病手当金」が支給されます。最長1年半まで1日あたりの給与の約2/3相当の手当金を受け取れます。
フリーランスにはこうした保障がありません。会社員のような有給制度もなく、怪我や病気で働けなくなると、収入がゼロになる恐れがあります。手術や通院が必要な場合、貯金だけで生活していくのは苦しいでしょう。
老後に想定される経済的リスク
老後もフリーランスと会社員で違いがあります。
会社員は「国民年金」と「厚生年金」の2階建てで加入していますが、フリーランスは「国民年金」のみです。したがって、フリーランスは老後に受け取れる年金が少なくなります。
フリーランスのリスクに備えるおすすめの保険
損害賠償や就業不能、老後などフリーランスのリスクに備えられる具体的な保険を紹介していきます。
フリーランス向けの賠償責任保険
フリーランス向けの賠償責任保険では、フリーランスとしての事業をするなかで受けた損害や賠償責任を補償してくれます。金銭的なトラブルが発生した場合、フリーランスは個人で対応しなくてはなりません。
ときには、個人では払えないような金額を請求される場合もあります。賠償責任保険で重大なトラブルによる破産に備えられます。
所得補償保険・就業不能保険
所得補償保険・就業不能保険は、病気やケガなどで働けなくなったときの所得を補償してくれる保険です。所定の就業不能状態になった際に毎月保険金を受け取れます。
もしものとき、日々の生活費の工面ができなくなるリスクに備えるためにも、検討したい保険の1つだといえるでしょう。
個人年金保険・確定拠出年金
個人年金保険・確定拠出年金は、老後に向けた資産形成におすすめです。
生命保険文化センターによると、老後の最低日常生活費用の平均額は月23.2万円でした。また、厚生労働省の「令和2年簡易生命表」によると、令和2年の平均寿命は男性が約82年、女性が約88年でした。
以上のことから、60歳以降の老後の生活費を考えると、老後に最低限必要な生活費は以下のように考えられます。
23.2万円×12か月×28年=7,795.2万円
上記の金額を残すには、計画的な貯蓄が欠かせません。老後に受け取れる年金の少なさをカバーするためにも、フリーランスは個人年金保険・確定拠出年金への加入を検討してみると良いでしょう。
亡くなった際に遺族が困窮するリスクに備える保険
フリーランスで働いている場合、亡くなった後に遺族が困窮する恐れがあります。2階建てで年金保険に加入していないフリーランスは、会社員と比べると受け取れる遺族年金の金額が少ないためです。
家族の死後は、収入源を失って日々の生活費に困るだけでなく、葬儀代を始めとした死亡整理金など、さまざまな費用がかかります。リスクに備える保険として「収入保障保険」と「定期保険」が挙げられます。
「収入保障保険」は、毎月あるいは毎年少しずつ保険金を受け取れ、遺族の生活費などをカバーできる保険です。
死亡保険の受け取りは、亡くなった時点から保険期間の残存期間となり、日が経つほど受け取れる総額は少なくなります。死亡保険のなかでは比較的保険料が安いのが特徴です。
「定期保険」でも、亡くなった際に遺族が死亡保険金を受け取れます。「収入保障保険」との違いは、保険金を一括で受け取れる点、保険期間内であればどの時点でも金額に変わりがない点です。
老後の生活資金が足りなくなるリスクに備える
老後は最低限7,795.2万円の生活費が必要ですが、国民年金だけで補うのは難しいと考えられます。計画的な貯蓄をするにあたって「終身保険」がおすすめです。
終身保険は、死亡保障もあり万が一に備えながら、老後に向けた資金作りもできる保険です。特徴として、途中解約をしても、解約返戻金を受け取れる点が挙げられます。老後資金だけでなく、子どもの学費の資金作りにも活用している人も多いです。
さまざまな特徴を持つ終身保険が存在するので、自分の目的にあったものを見つけやすいのではないでしょうか。
民間保険への加入もおすすめ
フリーランス協会の「ベネフィットプラン」では、「賠償責任保険」が自動付帯されます。情報漏洩や納期遅延、納付物の瑕疵、業務上の対物・ 著作権侵害などフリーランスに起こりうる賠償リスクへの補償がされます。
発注主も保障対象となるため、加入していると安心して発注してもらいやすくなるのも特徴です。さらに、「所得補償プラン」や「フリーガル」など任意で加入できる保険サービスも充実しています。
「所得補償プラン」は、怪我や病気、介護で働けないときに保険金を受け取れるサービスです。「フリーガル」は報酬に関するトラブル発生・予防において弁護士のサポートを受けられるサービスです。
フリーランスで健康保険に入らない場合のリスク
フリーランスとして働く場合、健康保険に加入しない選択をすると、いくつかのリスクや罰則が発生する可能性があります。日本では、国民皆保険制度のもと、すべての人が公的な健康保険に加入する義務があり、未加入の状態が続くとさまざまな不利益を被ることになります。
健康保険に未加入であると、病気やケガの治療費を全額自己負担しなければならず、医療費の負担が大きくなります。また、長期間未加入の状態が続いた場合、後から国民健康保険に加入しようとすると、過去の未納分を一括で請求される可能性があるため、支払いが困難になることも考えられます。
フリーランスになった際は、健康保険の未加入リスクを理解し、自分に合った制度を選択することが重要です。
フリーランスの保険に関するよくある質問
フリーランスの保険に関するよくある質問は以下の3つが挙げられます。
Q. フリーランスでも社会保険に加入できる?
Q. フリーランスが払う国民健康保険料はいくら?
Q. 会社員の健康保険と国民健康保険はどちらが安い?
最後まで見ることで、フリーランスの保険に関してより詳しくなり、保険でよくある失敗を防ぐことができるでしょう。
Q. フリーランスでも社会保険に加入できる?
フリーランスでも、条件次第では社会保険への加入できます。たとえば勤めていた会社の健康保険を任意継続する方法がその1つです。また、フリーランスをしながらアルバイトをしていたり、会社員がフリーランスとして副業をしている場合は加入可能です。
Q. フリーランスが払う国民健康保険料はいくら?
国民健康保険料は、住んでいる地域や年齢によって率が異なります。さらに、前年度の所得をもとに算出されるため、一概にいくらとはいえません。練馬区に住む30代で所得が500万円だと仮定したところ、およそ303,068円(1ヶ月あたり 25,256円)でした。
Q. 会社員の健康保険と国民健康保険はどちらが安い?
会社員の健康保険料と国民健康保険を比較すると、所得金額に関わらず健康保険料のほうが安いといえます。
※本記事は2025年2月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
簡単4ステップ!スキルや経験年数をポチポチ選ぶだけで、あなたのフリーランスとしての単価相場を算出します!
※相場算出に個人情報の取得はおこないません。
役に立った/参考になったと思ったら、シェアをお願いします。











