月収70万円の手取りや生活レベルとは?さらに年収を上げる方法も解説 | レバテックフリーランス
月収70万円の手取りや生活レベルとは?さらに年収を上げる方法も解説
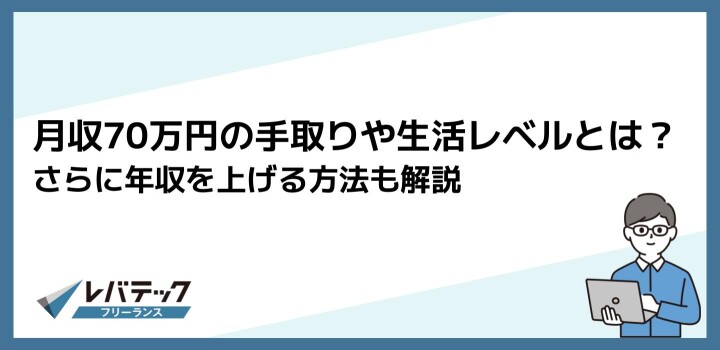
月収(額面)70万円の場合の手取りは、約53万円です。ただし、これは一定の条件をもとにしたシミュレーションです。実際の手取り額や年収は現住所や働き方によって異なるため、自分の条件で確認することが重要になります。
そこで、月収70万円の人の手取りを計算する方法や支払う税金・保険料について詳しく解説します。月収70万円の人の割合や生活レベルなども紹介しますので参考にしてください。
レバテックフリーランスはITエンジニア専門の
フリーランスエージェントですまずは相談してみる
■この記事の監修
武純(たけじゅん)

大手電機メーカーで1985年から2020年まで、プログラマー/インフラエンジニア/品質管理エンジニアとして長く活動していました。 その後、派遣エンジニアとしてプログラマー/インフラエンジニアとして2年勤めました。 主にC言語によるプログラミングと、Linuxによるインフラ構築を得意としています。
目次
月収70万円の手取り額は約53万円
月収70万円のときの手取り、つまり収入から経費や税金を差し引いた金額の目安は約53万円で、内訳は以下のとおりです。
| 月収 | 700,000円 |
|---|---|
| 所得税 | 52,217円 |
| 住民税 | 44,217円 |
| 国民年金 | 16,520円 |
| 国民健康保険 | 55,404円 |
| 手取り額 | 531,642円 |
世田谷区在住/30歳/独身・扶養なし/国民年金加入/常駐型フリーランス/青色申告/月額経費10万円の場合
- 所得の算出方法:(月額単価×12ヶ月)-(経費×12ヶ月)
- 税・年金・保険額:年間所得額をもとにした所得税/住民税(世田谷区)/国民健康保険額÷12ヶ月
- 消費税:前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合として算出
上記シミュレーションは2023年4月時点の法令に基づいた簡易的なものです。さらに、収益に経費を含めていないので、実際の支払額とは異なるでしょう。あくまでも目安と認識してください。
月収70万円の手取り計算方法
フリーランスの手取りの基本的な計算方法は、以下のとおりです。
収入-(必要経費+税金+保険料)=手取り額
必要経費(経費)とは、通信費や備品の購入費用など、事業運営にかかる費用のことです。どれくらいの経費がかかるかは、フリーランスの職種や業務内容によって異なります。
フリーランスと会社員の手取りの違い
一般的に、フリーランスの手取りは会社員と比べて少なくなる傾向にあります。会社員の手取りが給与の約75〜85%なのに対し、フリーランスは収入の60〜70%ほどになるとされています。
フリーランスの報酬とは異なり、会社員の給料には個人事業税と消費税が課されないためです。会社員が健康保険や年金保険料を会社と折半して納めるのも、フリーランスとの違いです。
確定申告の段取りについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
遅延すればペナルティも?期間内に正しく確定申告をしよう!
月収70万円の年収と手取り
月収70万円の年収は、ボーナスを含まない場合は840万円です。月給1ヶ月分のボーナスがある場合は70万円が加わり、年収910万円となります。月給2ヶ月分のボーナスがある場合は、140万円が加わり年収980万円となります。
大まかな手取り金額を求める際には、年収に0.7〜0.8をかけると便利です。ボーナスがない年収840万円の場合は約600万円、月給2ヶ月分のボーナスがある年収980万の場合は約690万円となります。
収入から引かれる税金と保険料
収入から引かれる税金と保険料には、所得税や住民税、国民健康保険料などを思い浮かべる人が多いでしょう。ほかにも、国民年金保険料や個人事業税、消費税などさまざまな支払義務が課せられています。実際に支払うものとそれぞれの概要を解説していきます。
所得税
所得税は、1年間の所得に応じて国に納める税金です。所得から経費や所得控除を差し引いた金額に対して課税されます。所得税には「累進課税制度」が適用され、所得が増えるほど税金が高くなる仕組みです。
たとえば、課税所得が195万円未満だと税率は5%で控除額は0円となります。195万円〜330万円未満の場合は、税率は10%で控除額は9万7,500円です。また、330万円〜695万円未満だと税率は20%で控除額は42万7,500円となります。
- 収入-経費=所得
- (所得-控除)×税率=所得税額
上記が所得と所得税額の計算式です。経費金額は人によってまったく異なるので、計算してみてください。
住民税
住民税は、住んでいる都道府県と市区町村に納める地方税の1つです。所得に応じて納税額が決まる「所得割額」と、自治体ごとに一律の税金を課す「均等割額」で成り立っています。
所得割額+均等割額=住民税額
上記のように、支払うべき住民税額は所得割額と均等割額の合計となります。
国民健康保険料
日本では、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入し、医療費を負担し合うことになっています。フリーランスは以下の場合を除き、基本的に市区町村運営の国民健康保険に加入します。
- 家族の扶養に入っている
- 前職の健康保険を任意継続している
- 職種別の国民健康保険組合に加入している
計算方法や料率は市区町村ごとに異なるため、お住まいの自治体のホームページをチェックしてみてください。
国民年金保険料
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務付けられています。フリーランス・個人事業主は基本的に第1号被保険者として保険料を納めます。
国民年金保険料は毎年改定がありますが、令和5年度(令和5年4月~令和6年3月まで)は月額16,520円です。
介護保険料
介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支えるシステムです。保険料を納めるのは65歳以上の第1号被保険者、および40歳〜64歳の第2号被保険者です。保険料の計算方法は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。
個人事業税
地方税の一種で、法律で定められた70業種を営んでいる場合に課される税金です。税率は3%〜5%で、業種ごとの区分によって異なります。
一律290万円の事業主控除があり「年間の所得が290万円に満たない場合は課税されない」といわれることもあります。ただし、青色申告特別控除が適用されない点に注意が必要です。個人事業税の計算方法は、以下のとおりです。
(所得金額-個人事業税の算出に適用される控除)×法定業種ごとの税率=個人事業税額
消費税
消費税は、商品の販売やサービスの提供に対して課される税金です。個人で活動するフリーランスの場合、前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合に納税義務が生じます。計算方法は以下のとおりです。
課税売上にかかる消費税額-課税仕入にかかる消費税額=消費税額
月収70万円の生活レベル
月収70万円のフリーランスの生活レベルについて世帯構造別に解説します。家賃・住宅ローンの目安、貯金についても触れているので参考にしてみてください。
独身の場合はかなり余裕がある生活
独身で月収70万円の場合、かなり余裕がある生活ができるといえるでしょう。趣味や娯楽、食事や衣料品などに自由にお金を使っていても、十分貯金できます。
| 家賃 | 130,000円 |
|---|---|
| 水道光熱費 | 15,000円 |
| 食費 | 60,000円 |
| 携帯代含む通信費 | 10,000円 |
| 交通費 | 10,000円 |
| 医療費 | 10,000円 |
| 趣味・娯楽費 | 60,000円 |
| 衣料品 | 30,000円 |
| 雑費 | 10,000円 |
| 貯金 | 195,000円 |
一般的に、手取りの20%ほどを貯金に回すのが望ましいといわれています。手取り53万円の20%は10万6,000円です。上記のような生活をしても、十分な貯金ができるといえるでしょう。
もっとも、今後一緒に暮らす相手が増えるほど、生活費はかかるものです。余裕のある一人暮らしのうちに、手取りの40%程度を貯金しておくと良いでしょう。
2人暮らしでも余裕がある生活が可能
月収70万円で2人暮らしをする場合でも、余裕のある暮らしが可能です。生活費は増えますが、それでも節約を意識しなくても十分貯金に回せると考えられます。
| 家賃 | 150,000円 |
|---|---|
| 水道光熱費 | 20,000円 |
| 食費 | 80,000円 |
| 携帯代含む通信費 | 10,000円 |
| 交通費 | 15,000円 |
| 医療費 | 20,000円 |
| 趣味・娯楽費 | 50,000円 |
| 衣料品 | 50,000円 |
| 雑費 | 10,000円 |
| 貯金 | 125,000円 |
ただし、支出の内訳を全く意識せずにお金を使っていくのは危険です。将来的に子どもが欲しい場合やマイホームの購入などを考えている場合、どれくらいの貯金が必要かを考えておくことをおすすめします。そのうえで、日ごろから支出を管理する習慣をつけておきましょう。
2人暮らし+子どもがいても貯金は可能
月収70万円で2人暮らしで子どもがいる場合でも、ある程度余裕もあり、貯金もしながら暮らしていけます。ただし、2人暮らしと比べると養育費などで支出は大きく増加します。
さらに、生命保険や学資保険に加入すると、2人暮らしのころの生活では手取りの20%の貯金は難しくなるでしょう。
| 家賃 | 150,000円 |
|---|---|
| 水道光熱費 | 25,000円 |
| 食費 | 80,000円 |
| 携帯代含む通信費 | 10,000円 |
| 交通費 | 15,000円 |
| 医療費 | 20,000円 |
| 趣味・娯楽費 | 40,000円 |
| 衣料品 | 30,000円 |
| 雑費 | 10,000円 |
| 保険代 | 10,000円 |
| 養育費 | 40,000円 |
| 貯金 | 100,000円 |
手取り20%の貯金をしたい人は、上記の表を参考に、自分の家庭ではどこを削れるのか見直してみてください。
月収70万円の家賃・住宅ローン
一般的に家賃の目安は手取りの30%と考えられています。そのため、月収70万円の人の場合の家賃は15万円〜16万円ほどが良いといえるでしょう。家賃15万円の物件となると、都区部でもファミリー向けの部屋を借りられます。
一般的に住宅ローン借入額は年収の5倍〜7倍程度だといわれています。したがって、住宅ローンの目安は3,500万円~4,900万円程度だといえるでしょう。
なお、無理なく返済できる比率は、手取り額の20%〜25%ほどだと考えられます。月収70万円なら、10万円〜13万円程度を考えておくのが良いでしょう。
返済以外にも、修繕費や固定資産税などの出費もあります。ほかにも、病気や怪我などの急な出費などをふまえた慎重な借入をするようにしましょう。
月収70万円の人の割合
月収70万円の場合、年収840万となります。令和3年分民間給与実態統計調査によると、年収800万円~900万円の人の割合は、全体で約2.9%という結果が出ています。男女別に見ると、男性は4.4%、女性は0.8%でした。
年収900万円を超える人の割合は全体で6.8%で、全体的に見てもかなり少ないといえるでしょう。
参考:令和3年分民間給与実態統計調査|国税庁
手取りを増やすコツ
フリーランスが手取りを増やすには、経費を漏らさず計上し、青色申告をするのが効果的です。また、フリーランス専用のエージェントを活用した案件獲得もおすすめです。
それぞれのメリットも紹介するので、把握したうえで実践し、手取りアップを目指しましょう。
経費をもらさず計上する
経費をもらさず計上して課税対象となる所得を減らして節税できれば、実質的な手取りアップにつながります。
ただし、そもそも何を経費にできるか知らないと、せっかく経費にできるものを計上しなかったという事態に陥りかねません。何を経費にできるのか詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
個人事業主が経費に計上できるもの一覧!上限や裏技的な方法も紹介
青色申告をする
フリーランスを含む個人事業主が確定申告をする際は、「青色申告」と「白色申告」のどちらかを選べます。青色申告をすると最大65万円の「青色申告特別控除」を受けられます。
65万円の控除を受けるには、複式簿記による帳簿作成、電子帳簿保存もしくはe-Taxを使用した申告などが必要です。節税を考えるならメリットは大きいでしょう。
青色申告は事前の申請が必要です。青色申告をする年の3月15日までに、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。その年の1月16日以降に事業を開始している場合は、事業を開始した日から2ヶ月以内となるため注意してください。
青色申告について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
青色申告と開業届を解説|個人事業主を始めるならば
転職や副業フリーランスをする
さらに年収を上げたいのであれば、スキルアップ転職やフリーランスとして副業をするのもおすすめです。
現在は人手不足で売り手市場の傾向もあるため、転職して年収アップに成功している人も多くいます。一度求人をチェックして検討してみるのも良いでしょう。
また、今の仕事を続けながらフリーランスの副業をするのもおすすめです。今の仕事のスキルを生かして、土日や空いた時間にできる仕事が見つかるかもしれません。
レバテックフリーランスでは、プロのコーディネーターがスキルや希望条件に合った案件を紹介しています。相談は無料なので、ぜひご検討ください。
月収70万円の手取りに関するよくある質問
月収70万円の手取り金額に関するよくある質問をまとめました。
Q. 月収70万円の場合の手取り金額はいくら?
月収70万円の手取り金額は約53万円です。約22万円は、国民健康保険・国民年金などの保険料や、所得税・住民税といった税金などで控除されています。
ただし、上記はあくまでこれは一定の条件をもとにしたシミュレーションです。保険料は住んでいる地域によっても異なるため、実際の手取り額は異なることにご留意ください。
Q. 一番得する年収の税金はいくら?
一番得する年収金額は、約600万円〜899万円だと考えられます。理由は、以下の所得税の税率にあります。
330万円~694万9,000円:20%
695万円~899万9,000円:23%
899万9,000円を超えると一気に33%となります。そのため、20〜23%の税率内の年収であると、得であると考えられるでしょう。
※本記事は2024年2月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
簡単4ステップ!スキルや経験年数をポチポチ選ぶだけで、あなたのフリーランスとしての単価相場を算出します!
※相場算出に個人情報の取得はおこないません。
役に立った/参考になったと思ったら、シェアをお願いします。












